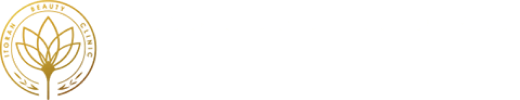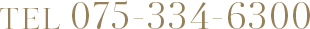子宮脱は若年層の女性でも起こり得る?治療法や原因も併せて解説
- 子宮脱は高齢女性だけでなく、出産経験のある若年層にも起こる可能性があります。
- 原因としては出産時の骨盤底筋へのダメージや遺伝的要素が挙げられます。
- 違和感や尿漏れなどの初期症状が見られたら、早めの受診が重要です。
- 治療法には骨盤底筋トレーニングやペッサリーの使用、手術などがあります。
- 早期に対応することで、日常生活への支障を最小限に抑えることができます。
- 予防のためにも日常的に骨盤底筋を鍛える習慣をつけることが効果的です。
子宮脱は婦人科の病であり、誰であろうと起こる可能性があります。
しかし一方で詳しいことを知っている人は多くありません。
特に中高年の年代に多いため、若年層の女性は知識のある人がさらに少なくなってしまいます。
しかし若年層だから関係ないと限ったわけではなく、若くても正しい知識は必要です。
本記事では子宮脱の症状や治療法、若年層との関係について解説します。
どの年代の人であっても参考にして、自分の体を大切にする助けにしてください。
子宮脱とは?

子宮脱とは、子宮が外部に出てしまっている症状のことです。
通常子宮は、骨盤底筋という筋肉などに支えられており、このおかげで外へ出ることなく膣内部に納まっています。
しかし骨盤底筋にトラブルが起こるなどの原因で、子宮が膣の外に出てしまうことがあります。
これが子宮脱です。
子宮脱の原因
子宮脱の原因は、主に以下のとおりです。
- 出産
- ホルモンバランスの影響
- 体調不良
一般的に若く健康であるほど、子宮脱の原因となる要素がありません。
若年層に詳しくない人が多いのも、そのためです。
出産
出産は子宮脱の大きな原因と言われています。
出産することで骨盤底が損傷し、その影響で子宮脱に繋がるのです。
実際に、子宮脱となった人の9割ほどは経産婦です。
ただし、出産直後に子宮脱になることはまれです。
出産後、体を回復しようとする治癒力が働き、その場は元に戻ります。
実際に影響が出始めるのは、60代くらいになってからが多いです。
ホルモンバランスの影響
ホルモンバランスの影響でも子宮脱の原因になることがあります。
正確に言うとホルモンバランスが直接の原因ではなく、ホルモンバランスの影響で骨盤底筋が弱くなってしまい、結果的に子宮脱になってしまうという流れです。
そのためホルモン剤を使った病気の治療や、閉経した人は注意が必要です。
外部の刺激
まれなケースではありますが、外部の刺激から子宮脱になる例もあります。
手で陰部を触るのがくせになってしまっていたり、ウォシュレットを過剰に当てたりということを継続していると、性器はダメージを受けてしまいます。
症例としてはほとんど見られず、かなりの低確率と言えますが、まったくないわけではありません。
子宮脱以外のトラブルに繋がる可能性も高いため、心当たりがある場合は生活習慣を改善しましょう。
若年層でも子宮脱になる?
結論から言うと、若年層の女性でも子宮脱にはなり得ます。
人数比では確かに少ない傾向にありますが、絶対にならないという保証はありません。
特にホルモンバランスに関しては、若い人でもなんらかの病気でホルモン剤を使用していたり、早発閉経で若くしてすでに閉経後の状態になっている人もいます。
「若いから自分は絶対に大丈夫だ」という考えは止め、機会があれば婦人科や美容クリニックにて診てもらうことをおすすめします。
【参考】子宮脱になりやすい年齢
現実として子宮脱になりやすい年齢のピークは、50~60代です。
出産を経験し、かつ閉経してホルモンバランスが崩れる。
この2つの条件の揃う人が増え始めるのが、50~60代という年齢層です。
出産していても、若い人に子宮脱発症者が少ないのは、閉経前でホルモンバランスがまだ崩れていないからともいえます。
とはいえ、出産して閉経していても、子宮脱にならない人は大勢います。
あくまでなりやすいというだけであり、出産して閉経したら必ず子宮脱になる、というわけではありません。
子宮脱の症状経過
子宮脱は突然始まる物ではなく、症状がだんだんとひどくなっていきます。
理想としては初期段階で気づければ治療も楽ですが、現実問題として多くの人はある程度症状が進まなければ気づきません。
また、気づいたとしても「今は忙しいから落ち着いたら…」と治療を後回しにし、ひどくなってからやっと病院に行くという人も少なくありません。
初期
初期症状は、子宮が体の中で通常より下へと動いてきます。
子宮下垂と言われる症状です。
しかし、この段階では何も感じないため、自覚症状だけで察することはほとんど不可能です。
初期症状の段階で気づく人の多くは、婦人科や美容クリニックに行き、医師に診てもらって指摘され気づくという流れです。
そのため、問題ないと思っても定期的に診てもらうことが大切です。
中期
症状が進むと、膣の部分に固く丸い感触を覚えるようになります。
大きさはピンポン玉くらいです。
異物感を覚えるため、多くの人はこの段階で発症に気づきます。
しかし、気づいたとしても違和感だけで、「生活に支障が無い」「その内治る」と考える人もいます。
その結果病院を後回しにしてしまうと、さらに症状が進みます。
後期
症状が最後まで進むと、子宮がよりはっきりと膣の部分に確認できるようになります。
また、子宮に引っ張られて、他の内臓が出てきている場合もあります。
下着などに擦れることもあり、痛みや出血を伴うようになります。
ここまで症状が進行した場合は、すぐに病院にかかり診てもらいましょう。
子宮脱になってしまったら
子宮脱になってしまった場合は、治療を行うことになります。
主な治療法は以下の3つです。
- 運動療法
- ペッサリーリング施術
- 外科手術
なお、これらはすべて同時に行うのではなく、自分にあった治療法を選んで行うことになります。
運動療法
運動療法とは、骨盤底筋を鍛え内臓が出てこないようにする治療法です。
軽度であれば、運動療法で回復することができます。
ただし、自分の状態が軽度に当てはまるのか、運動療法で回復可能であるのかは、診療されるまでわかりません。
くれぐれも自己判断は止め、医師に診てもらいましょう。
ペッサリーリング施術
ペッサリーリング施術とは、ペッサリーリングを膣内に挿入する治療法です。
リング状の形をしたペッサリーリングを膣内に入れることで、内臓がリングに引っかかり、それ以上外に出てこないようになります。
負担が軽いため、手術などの体力が無い人に適しています。
反面2~3カ月に1回の交換が必要であり、根本的な解決にはなっていないとも言えます。
外科手術
子宮脱になり症状がある程度進んでいると、一般的には外科手術で治療することになります。
従来は子宮が出てくる入口部分を縫い留めるのが一般的でしたが、最近では膣と臓器の間に壁を作り支える方法が、新たな術式として知られています。
女性器のお悩みはいとうらんクリニックにご相談を

子宮脱に限らず、女性器のトラブルは言いづらくデリケートなものです。
もしも「相談したいけれど当てが無い…」という場合は、ぜひいとうらんクリニック四条烏丸にてご相談ください。

記事監修医師プロフィール
院長/形成外科専門医・医学博士
伊藤 蘭
| 2003年 | 山口大学医学部卒業 |
|---|---|
| 2003年 | 京都大学医学部附属病院形成外科 日本赤十字社和歌山医療センター形成外科 |
| 2006年 | 島根県立中央病院 形成外科 |
| 2008年 | 松寿会共和病院 形成外科 |
| 2010年 | 京都大学大学院医学研究科課程博士(形成外科学)入学 |
| 2012年 ~2014年 | MD Anderson Cancer Center, Houston, USA. (Microsurgery Research Fellow) |
| 2014年 | Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan(Microsurgery Fellow) |
| 2014年 | 京都大学大学院医学研究科課程博士(形成外科学)博士課程 所定の単位修得および研修指導認定 |
| 2015年 | 京都大学医学部附属病院形成外科 助教 |
| 2017年 | 城本クリニック京都院 院長 |
| 2020年 | ピュアメディカル西大寺院 院長 |
| 2021年 | くみこクリニック四条烏丸院 院長 |
| 2022年 | いとうらんクリニック四条烏丸開設 |