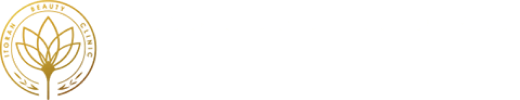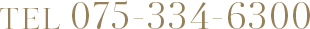医療ハイフの持続性は長いって本当?施術間隔やリスクを解説!
- 医療ハイフの持続効果が長い理由やメカニズムをわかりやすく解説します。
- 効果が出るまでの期間や回数の目安、施術間隔について具体例を示します。
- 腫れや痛み、赤みなどのリスクや副作用の出方を整理します。
- 適応できないケースや注意が必要な人の特徴を具体的に紹介します。
- 施術後のケア方法や生活上の注意点、効果を維持するポイントを解説します。
- 安全に施術を受けるための確認事項や医師選びのポイントを提示します。
医療ハイフはメスを使わずに行えるリフトアップ治療として人気です。
しかし、メスを使わない分、持続期間も短いのでは?と思っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、医療ハイフでリフトアップできる仕組みと持続期間について解説しています。
医療ハイフの持続期間を知って、施術を受ける際の参考にしてください。
医療ハイフとは

医療ハイフとは、高密度焦点式超音波(High Intensity Focused Ultrasound)という技術を使ったリフトアップ施術です。
皮膚の奥と、筋肉の間にSMAS層と呼ばれる筋膜があります。
加齢によってこのSMAS層がゆるむと、肌の土台が地すべりと同じ原理で支えられなくなり、肌がたるみます。
そこで、超音波の熱エネルギーをSMAS層に照射し、SMAS層とその上の真皮層をキュッと引き締めるのが医療ハイフです。
熱エネルギーによって、SMAS層が引き締まるのは、焼いた肉が縮むのと似ています。
SMASと真皮層の土台をしっかり固めることで、たるみの解消を図るのが医療ハイフです。
また、医療ハイフでは脂肪細胞を破壊できます。
痩身やダイエット目的でも使えるのが医療ハイフのメリットです。
医療ハイフの効果はいつから表れる?
医療ハイフでは次の3点の効果が期待できます。
- SMAS・真皮層の引き締め
- コラーゲン・エラスチンが作られることによる内側からのハリ増加
- ダイエット・痩身
1の場合、即効性が高く、施術後すぐから引き締まった実感があるでしょう。
一方、2の場合、コラーゲン・エラスチンの産生には1ヶ月程度かかります。
3のようなダイエット目的の場合、ハイフによって破壊された脂肪細胞が、排泄などで体の外に出るまで1~3ヶ月程度かかります。
そのため、引き締めは施術直後、それ以外は数ヶ月かかることを覚えておきましょう。
医療ハイフの持続性
医療ハイフは、残念ながら一度施術を受けたからといって、永久的にたるみが改善されるわけではありません。
ここからは、医療ハイフの持続性をリフトアップ・ダイエットの目的別に解説していきましょう。
リフトアップ目的の場合:半年から1年
リフトアップが目的の場合、医療ハイフの持続期間は半年から1年です。
医療ハイフは、施術直後でもある程度効果が実感できます。
しかし、たるみの引き締めやハリ増加を実感するには、施術から1ヶ月程度かかります。
あまり実感がないからと言って、短い期間に何度も施術を受けても効果が上がるわけではありません。
肌ダメージにつながる可能性があるので、適切な間隔で照射しましょう。
医療ハイフは、施術半年ごろで、再度たるみが気になり始めます。
クリニックに相談して、次回の施術を決めていきましょう。
ダイエット目的の場合:半永久
医療ハイフで、一度破壊した脂肪細胞は元に戻りません。
「成人では脂肪量の主要な決定因子は体内の脂肪細胞数だが、その数は小児期から青年期に決まり、成人になってからはほとんど変化しない。」
(引用:nature日本版 2008年6月5日号)
成人以降、脂肪細胞の数がほとんど変化しないとすれば、医療ハイフによって破壊された分の脂肪は増えません。
したがって、脂肪細胞の数を減らせるという意味で、ダイエット目的の場合は半永久的な効果も期待できます。
医療ハイフの施術間隔
医療ハイフを受ける場合、どのくらいの間隔で受ければいいのでしょうか。
ここからは医療ハイフの施術間隔について解説していきます。
顔の施術間隔
リフトアップ目的で、医療ハイフを顔に施術する場合は、3ヶ月~半年ごとに施術を受けるのがおすすめです。
なぜなら内側からハリが出るまでに時間がかかり、時間を置くことで肌ダメージも改善するからです。
施術から1ヶ月ほどで、コラーゲン増産によるハリが出ますが、施術から6ヶ月経過するころには、ハリ感も徐々に失われていきます。
間隔が短すぎることで起きるデメリットを避けるため、施術から3ヶ月以上経過して、たるみが気になり始めたらクリニックに相談へ行きましょう。
ボディの施術間隔
ダイエットや部分的な引き締めを目的に医療ハイフを受ける場合、施術間隔は3~4週間に1回がおすすめです。
脂肪細胞は一気に破壊できないので、少しずつ医療ハイフを照射する必要があります。
医療ハイフは、他の痩身治療と組み合わせて行うことができます。
種類によっては間隔を空けなければなりませんが、他の施術と組み合わせることで、理想のボディラインを手に入れやすくなります。
医療ハイフをやりすぎることで生じるリスク
医療ハイフは、メスを使わず、照射だけでリフトアップ・部分痩せ効果が期待できる施術です。
しかし、体質・肌質によっては、医療ハイフのやりすぎでリスクが起こることもあります。
ここからは、医療ハイフをやりすぎることで生じるリスクを紹介します。
疲れて見える
1つ目のリスクは「疲れて見える」ことです。
もともと顔の皮下脂肪が少ない方が医療ハイフを受けると、脂肪細胞が破壊されて頬がこけるなどのリスクがあります。
頬や目の下がこけると疲れて見え、何のためにハイフを受けたのかわかりません。
皮下脂肪が少ない方で、肌のたるみが目立つ方は切開リフトなど別の選択肢もあります。
皮膚のたるみ
皮下脂肪が少ない方が医療ハイフをやりすぎると、頬がこける以外にも、脂肪がなくなることで肌内部のクッションが減り、肌がたるむことがあります。
また、医療ハイフそのものの刺激で肌がたるむことも考えられるでしょう。
皮膚のたるみがもともと大きい方は、医療ハイフ向きではありません。
他の方法でたるみを改善するのがおすすめです。
いとうらんクリニック四条烏丸のハイフは部分痩せの持続性が高い
いとうらんクリニック四条烏丸では、医療ハイフにNEWダブロを導入しています。
フェイシャルとボディでそれぞれ照射出力を変えているので、目的に応じた照射が可能です。
筋トレで落としにくい二の腕や脇腹、膝上のもたつきなど、ボディはセット照射メニューも用意しています。
医療ハイフで痩身をしたい方は、痛みの説明も行っておりますので、ご相談にお越しください。
【まとめ】医療ハイフは目的で持続性が変わる 適切な間隔で施術を受けよう

医療ハイフは、たるみの引き締め・リフトアップ目的で行うのか、または部分的なダイエット目的で行うのかで持続性が変わります。
顔の場合3ヶ月から半年を目安に、体の場合は3~4週間に1回を目安に施術計画を立てましょう。
医療ハイフは、継続治療を行うことで、ハリを実感しやすくなります。
自分に合ったサイクルで通えるクリニックを見つけていきましょう。

記事監修医師プロフィール
院長/形成外科専門医・医学博士
伊藤 蘭
| 2003年 | 山口大学医学部卒業 |
|---|---|
| 2003年 | 京都大学医学部附属病院形成外科 日本赤十字社和歌山医療センター形成外科 |
| 2006年 | 島根県立中央病院 形成外科 |
| 2008年 | 松寿会共和病院 形成外科 |
| 2010年 | 京都大学大学院医学研究科課程博士(形成外科学)入学 |
| 2012年 ~2014年 | MD Anderson Cancer Center, Houston, USA. (Microsurgery Research Fellow) |
| 2014年 | Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan(Microsurgery Fellow) |
| 2014年 | 京都大学大学院医学研究科課程博士(形成外科学)博士課程 所定の単位修得および研修指導認定 |
| 2015年 | 京都大学医学部附属病院形成外科 助教 |
| 2017年 | 城本クリニック京都院 院長 |
| 2020年 | ピュアメディカル西大寺院 院長 |
| 2021年 | くみこクリニック四条烏丸院 院長 |
| 2022年 | いとうらんクリニック四条烏丸開設 |